パワハラ防止法は 「パワハラの明確化」+「企業の防止義務」 を柱とし、働きやすい職場環境を作るためのルールを定めたものです。
消防職員という特殊な職場での パワハラ防止対策 (改正労働施策総合推進法)について、消防は上下関係や規律を重視する組織文化があるため、パワハラと「必要な指導」の線引きが難しい点が特徴と思われます。パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)について投稿させて頂きます。
制定の背景
- 職場における パワーハラスメント(パワハラ) が社会問題化。
- 厚労省調査でも「職場のいじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が労働相談で最多水準。
- 働きやすい職場環境整備のため、2019年に法改正。
法律の位置づけ
- 正式名称:労働施策総合推進法(改正部分)
- 通称:パワハラ防止法
- 職場におけるパワーハラスメント対策が
令和2年(2020年)6月1日から大企業の義務になりました!
令和4年(2022年)4月1日から中小企業の義務になります!
職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに事業主の義務になりました。
パワハラの定義
職場におけるパワハラとは、次の3要件を満たす行為。
- 優越的な関係を背景に行われること
(上司→部下だけでなく、同僚間や部下→上司も含む) - 業務の適正な範囲を超えた言動であること
- 労働者の就業環境を害すること
典型的な行為類型(厚労省指針による6類型)
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・侮辱・過度な叱責)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し)
- 過大な要求(遂行不可能な業務の強要)
- 過小な要求(能力や経験に見合わない単純作業の強制)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
企業の義務
パワハラ防止のための雇用管理上の措置 が義務化
- 就業規則や社内方針での明確化
- 相談窓口の設置
- 相談があった場合の迅速・適切な対応
- 被害者・加害者双方のプライバシー保護
- 再発防止策の実施
罰則・行政対応
- 直接的な刑事罰・民事罰はなし。
- ただし、企業が措置義務を怠ると 厚生労働省が勧告・企業名公表 する可能性あり。
- 被害者は 労災認定・民事訴訟 などで救済を受ける場合もある。
セクハラ・マタハラとの関係
-
セクハラ(男女雇用機会均等法)、マタハラ(育児介護休業法)と並び、職場ハラスメント防止の三本柱 として企業対応が求められる。
消防職員という特殊な職場での パワハラ防止対策
消防職場におけるパワハラのリスク
- 階級社会・命令系統が明確 → 指導が「強圧的」に感じられやすい。
- 肉体的・精神的に厳しい訓練や勤務 → 行き過ぎると「過大要求」「身体的攻撃」に該当。
- 閉鎖的な職場環境(24時間勤務・小集団) → 「人間関係からの切り離し」が起きやすい。
- 伝統・慣習の継承 → 「昔はこうだった」という文化がハラスメント温床になり得る。
消防職員向けパワハラ防止対策
明確なルールと方針の周知
- 消防局・消防本部として 「パワハラを許さない」方針を明文化。
- 「適正な指導」と「パワハラ行為」の違いを例示し、職員に共有。
- 例:火災現場での厳しい指示=OK/人格否定を伴う叱責=NG
相談体制の整備
- 内部相談窓口(人事課、安全管理室など)の設置。
- 外部相談機関(弁護士・カウンセラー)との連携。
- 匿名相談の仕組みを導入し、声を上げやすくする。
幹部・指導層への研修
- 指導方法のアップデート:厳しさの中にも尊重を持つ指導法。
- ハラスメント事例学習:過去の不祥事をケーススタディにする。
- 心理的安全性の理解:隊員が意見を言いやすい環境作り。
若手・新人へのフォロー
- メンター制度(班長や中堅職員が相談役)。
- 定期的なヒアリングで職場環境を把握。
チーム文化の改革
- 「厳しさ=成長」から「支え合い=強さ」へ価値観をシフト。
- 訓練や勤務後にフィードバック+労いの声かけを取り入れる。
消防特有の工夫例
- 訓練チェックリスト:訓練の負荷が「過大要求」に当たらないかを評価。
- 心理的安全性サーベイ:隊ごとに定期調査。
- 事例共有会:他本部での成功事例や失敗事例を学ぶ場を設定。
消防職員向けパワーハラスメント防止マニュアル(草案)
本マニュアルは、消防職員が安全かつ健全に勤務できる職場環境を確保するために、
パワーハラスメント(以下、パワハラ)の防止・早期発見・適切対応を図ることを目的とする。
パワハラの定義
職場におけるパワハラとは、以下の3要件を満たす行為をいう。
- 優越的な関係を背景に行われること
- 業務の適正な範囲を超えた言動であること
- 職員の就業環境を害すること
典型的な行為類型(消防現場例を含む)
- 身体的攻撃:殴打、蹴り、訓練中に安全配慮を欠いた体罰
- 精神的攻撃:人格を否定する暴言、過度な叱責
- 人間関係からの切り離し:特定職員の排除、班内での孤立化
- 過大な要求:不可能な訓練や長時間の無理な勤務命令
- 過小な要求:経験者に不必要に簡易な業務しか与えない
- 個の侵害:私生活への過度な干渉、家庭事情の軽視
指導とパワハラの区別
消防職場では規律と緊張感が求められるため、次のように区別する。
適正な指導
- 火災現場での迅速かつ厳格な指示
- 訓練中に改善点を明確に伝える注意
- 職務遂行に必要な基準を示す行為
パワハラに該当する可能性のある行為
- 指導の目的を逸脱し、感情的に怒鳴り続ける
- 個人の人格や家庭環境を否定する発言
- 明らかに遂行困難な訓練・勤務を命じる
組織としての防止措置
方針の明文化
- 本部長名で「パワハラを許さない」メッセージを職員へ周知。
相談窓口の設置
- 内部窓口(人事、監察、安全管理担当)
- 外部機関(弁護士、臨床心理士)との連携
- 匿名相談の受付体制
教育研修の実施
- 幹部職員:指導方法研修、事例研究
- 全職員:パワハラ防止研修、ケーススタディ
職場環境の把握
- 定期的なアンケート調査やヒアリング
- 結果に基づく改善計画
パワハラを受けた(目撃した)ときの対応
受けた本人
- まずは信頼できる上司・相談窓口へ報告
- 記録(日時・状況・発言内容)を残す
目撃した職員
- 速やかに相談窓口や管理者へ報告
- 被害者へのフォローを行う
相談対応の流れ
- 相談受付(窓口・担当者が秘密保持を厳守)
- 事実確認(関係者へのヒアリング)
- 必要に応じた暫定措置(配置変更、接触制限など)
- 調査結果に基づく対応(指導、処分、再発防止策)
- 被害者へのアフターフォロー
再発防止
- 問題が発生した場合は必ず原因を分析し、改善策を職場全体で共有。
- 指導担当者への研修を強化。
- 職員間で「声をかけ合う文化」「互いを尊重する文化」を育成。
運用・見直し
- 本マニュアルは定期的に見直し、最新の法令・判例・事例に基づき改訂する。
- 改訂内容は全職員へ周知徹底する。
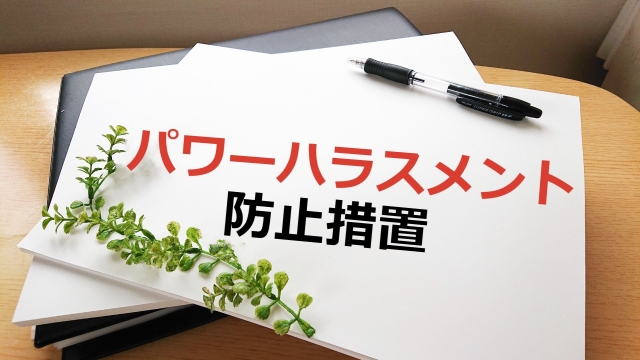













コメント